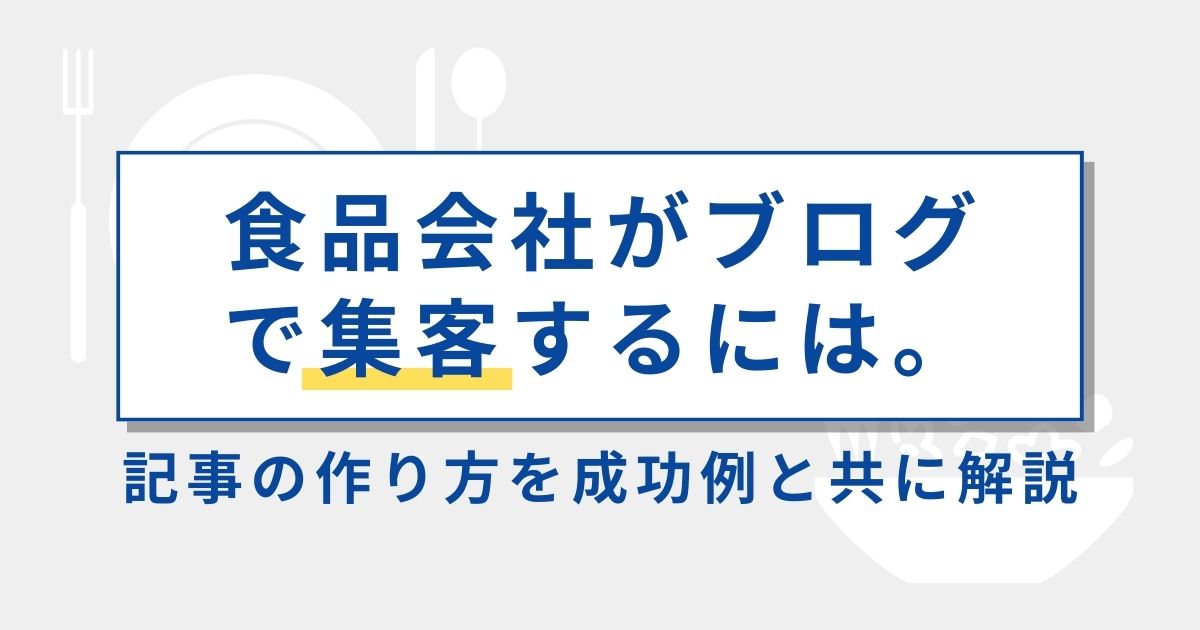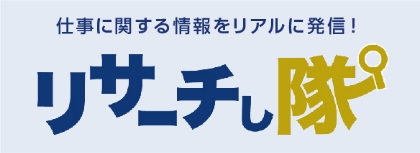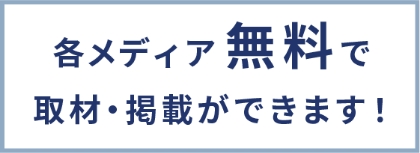SEO対策を行う上で、記事構成の設計は「成果の8割を決める」と言われるほど重要な工程です。
しかし、まだ経験が浅い方は 「上位記事を真似してもうまくいかない」「どうやって構成を組み立てればいいの?」と悩むことも多いでしょう。
SEOで結果を出し、上位表示させるためには、ユーザーニーズを深く理解することが不可欠です。
この記事では、ユーザーニーズを捉えたSEOに強い記事構成を作る方法と、初心者が陥りがちな落とし穴を解説します。
さらに、競合と差別化し、独自の価値を生み出すためのポイントまでご紹介します。
ぜひ最後までご覧いただき、ユーザーにとって価値のあるコンテンツ作成にお役立ていただければ幸いです。
弊社では、札幌のWEB制作・マーケティング支援のプロ集団として、企業の成長をサポートしています。
お客様の価値を最大限に引き出すご提案をさせていただきますので、
北海道で集客にお悩みの方は、ぜひお気軽にご相談ください。
まずは1時間無料相談SEO記事の構成を作る上で欠かせないのは「検索意図」の理解
SEO記事を構成するうえで最も重要なのは、検索ユーザーがどんな情報を求めているのか(ニーズ)、つまり「検索意図」を掴むことです。
顕在ニーズ:ユーザー自身が気づいている「知りたいこと」
潜在ニーズ:ユーザー自身もまだ気づいていない「関連情報」
記事構成では、この両方を満たすことが重要です。
まずは顕在ニーズを満たし、記事の中盤~後半にかけて潜在ニーズに応えていくことで、ユーザーの満足度を120%満たせる記事になるでしょう。
【ユーザーニーズを掴む】SEOに強い記事構成の作り方
SEO記事を作る上で重要な「ユーザーニーズ」を正しく把握するために、どのような手順を踏むべきなのか迷ってしまうこともあるでしょう。
ここでは、初心者でもすぐに実践できる「ユーザーニーズを調査する具体的な手順」と、実際の記事構成に落とし込むまでの方法を紹介します。
ぜひ、記事作成の参考にしてみてください。
①キーワードから検索意図を掴む
SEOコンテンツの構成作りの第一歩は、「ユーザー理解」です。
- 主キーワードで実際に検索をかける
- サジェストキーワード・共起語・関連キーワードを確認
- Yahoo!知恵袋やYouTubeのコメント欄、SNSなどでユーザーの「生の悩み」を拾う
このような調査で、ユーザーが抱えているリアルな疑問を把握することが可能です。
特に、知恵袋やSNS等のリサーチは、競合が見落とす切り口を見つけるチャンスにもなります。
また、「誰が」「どんな悩みで」「何を知りたいのか」を明確にしなければ、ユーザーにとって響く記事にはなりません。
キーワードを単語ごとに区切り、それぞれ「5W1Hの観点から理由を深掘りする」ことで、ユーザーニーズがより具体的に見えてくるようになるでしょう。
- いつ(When)
- どこで(Where)
- 誰が(Who)
- 何を(What)
- なぜ(Why)
- どのように(How)
こちらは深いユーザー理解に欠かせないフレームワークなので、ぜひ積極的に活用してみてください。
②上位記事を徹底分析する
Googleは「結果指標」のため、現時点で検索上位に出ている記事は、1つの「正解」と捉えることができます。
上位記事が「どのような情報を取捨選択しているか」を分析することで、ペルソナ像やニーズの傾向を掴むことができるでしょう。
- 見出しを抽出し、どんな傾向で情報を取捨選択しているか
- 上位記事(1位~5位程度まで)に共通して登場する見出し(=ユーザーの強いニーズ)
- リード文で想定している読者像
ただし、以下のような注意点もあります。
- 上位記事の見出しをそのままコピーするのはNG
- 全て網羅する=正解ではない
- ドメインパワーで順位が高いだけの記事もある(コンテンツの質が必ずしも高いとは限らない)
重要なのは、「ユーザーのニーズを的確にとらえ、欲しい情報を与えられているか(ユーザーに刺さる構成になっているか)」という点です。
③ペルソナを具体的にイメージする
- 上位記事のリード文や書き方から、ペルソナ(読者像)を想定
- Yahoo!知恵袋やSNS、YouTubeのコメント欄などで、ユーザーの「生の声・悩み」を拾う
- ペルソナが複数考えられる場合は、自社サービスと相性がいいターゲットに絞る
複数のペルソナを全方位に狙おうとして「誰にも刺さらない記事」になってしまうこともあります。
そのため、狙う方向性は明確にしておくことが大切です。
④ 階層構造を意識して見出しを設計する
見出し構成を作る際は、「階層構造」になるよう組み立てていきます。
H2にはトピックの大枠を、H3には、 H2の主張を深掘り、補完する内容を配置します。
例えば、
H2:SEO記事構成の作り方
┗H3:①キーワードを整理する
┗H3:②見出しの順番を考える
このように、H3は必ず上位のH2と流れがつながっている必要があります。
見出しの階層構造が崩れると、情報が散らかって読みづらくなり、SEO的にも不利になってしまうため注意しましょう。
SEO記事の「独自性」を高めるコツ
SEOで成果を出すためには、“この記事でしか得られない価値”を提供する「独自性」が欠かせません。
差別化のコツは、実体験やデータなどの「一次情報」と、筆者ならではの「独自の視点」です。
ここでは、他の記事と差別化を図るために意識したいポイントを解説します。
情報源をずらす
ネット上でのリサーチだけでなく、書籍や動画・SNS・取材など、インプットする情報源をずらすことで、他の記事にはないオリジナリティを出しやすくなります。
特に、クライアントや顧客へのヒアリング、アンケート結果などは、貴重な一次情報として活用することができます。
- 実際の体験や事例
- クライアントやユーザーの声
- 書籍・セミナー・インタビューなどの一次情報
こうした「まだネット上に存在しない情報源」を活用することで、記事に独自性が生まれ、ユーザーにとって「価値あるコンテンツ」として、Googleからの評価も上がることでしょう。
アウトプットを工夫する
例えば解説記事なら、どこよりもわかりやすくかみ砕いて説明するなど、読者への伝え方・表現方法を工夫することも差別化要素になります。
また、自分が実際に得た経験や仮説に基づく主張を加えるのも良いでしょう。
「自分はこう分析している」「こう考えた結果こうなった」など、独自の視点を入れることも効果的です。
SEO記事作成の注意点|初心者が陥りがちな5つの罠
SEOの記事構成を作る上で、初心者が陥りがちなポイントを理解しておくことも重要です。
ここでは、特に意識したい注意点を5つ紹介します。
- 上位記事の構成を真似した「コピー記事」になってしまう
- 「上位記事=絶対的な正解」と思い込んでしまう
- 競合サイトの切り口に引っ張られて思考停止する
- 情報の取捨選択を誤る
- 見出しの順番を誤る
以下で詳しく見ていきましょう。
①上位記事の構成を真似した「コピー記事」になってしまう
検索結果の上位記事をいくつか参照した際、それぞれ内容や想定ターゲットが少しずつ異なる場合があることに気づくはずです。
これは、Googleが「情報の多様性」を重視しているためと考えられています。
同じような内容の記事は一つで十分だと判断されるため、競合を真似しただけの構成では上位表示されません。
上位記事はあくまでも参考程度に留め、「すでに存在する記事と似たコンテンツは不要」という意識を持つことが大切です。
②「上位記事=絶対的な正解」と思い込んでしまう
上位に表示されている記事だからといって、必ずしもコンテンツの質が高いとは限りません。
なぜなら、 上位サイトは記事の内容だけでなく、ドメインパワーや被リンク、ブランド力などで評価されている場合もあるからです。
それを知らないまま、上位記事の内容を鵜呑みにしてしまうことがないようにしましょう。
③競合サイトの切り口に引っ張られて思考停止する
上位記事を参考にしすぎると、新たな切り口を考えるプロセスを飛ばしてしまいがちです。
対策としては、一度自分の頭で仮説を立て、構成を考えたあとに上位記事を確認することで、オリジナルの要素を生み出しやすくなるでしょう。
④ 情報の取捨選択を誤る
ユーザーにとって必要な情報が抜けてしまったり、逆に不要な情報を入れてしまったりすることも、よくある失敗です。
常に「ユーザー視点」で、自分が読み手だったらどう感じるか、どのような情報が知りたいか、といったことを考える癖をつけるのがおすすめです。
⑤見出しの順番を誤る
見出しはユーザーが最も知りたい重要な要素から、順番に並べていきます。
検索して最初に求めている情報(=顕在ニーズ)は、記事の前半に配置し、背景・理由・関連情報(=潜在ニーズ)を中盤~後半に入れることで、ユーザーの満足度を一層高めることができるでしょう。
まとめ:記事構成は「ユーザーニーズの理解」が鍵になる
SEOに強い記事構成を作る上で欠かせないのは、検索意図やユーザーニーズを正しく理解することです。
この記事で紹介したポイントを押さえれば、読者にとって価値あるコンテンツを作りやすくなるでしょう。
しかし、こうした設計・分析・運用を自社だけで行うには、多くの時間・労力・専門知識が必要です。
もし社内で手が回らない場合は、コンテンツマーケティングで数多くの実績を持つエレメントにお任せください。
私たちは、WEB制作とマーケティングの両面から成果創出を支援する、札幌のプロフェッショナル集団です。
特に、SEOに特化したコンテンツマーケティングにおいて、多くの企業様にご評価いただいております。
成功事例は、以下のボタンよりご覧いただけます。
成功事例を見てみるまた、お客様の強みを言語化し、戦略に落とし込むご提案も可能です。
無料相談も受け付けていますので、まずは一度お気軽にご相談ください。
お問い合わせ